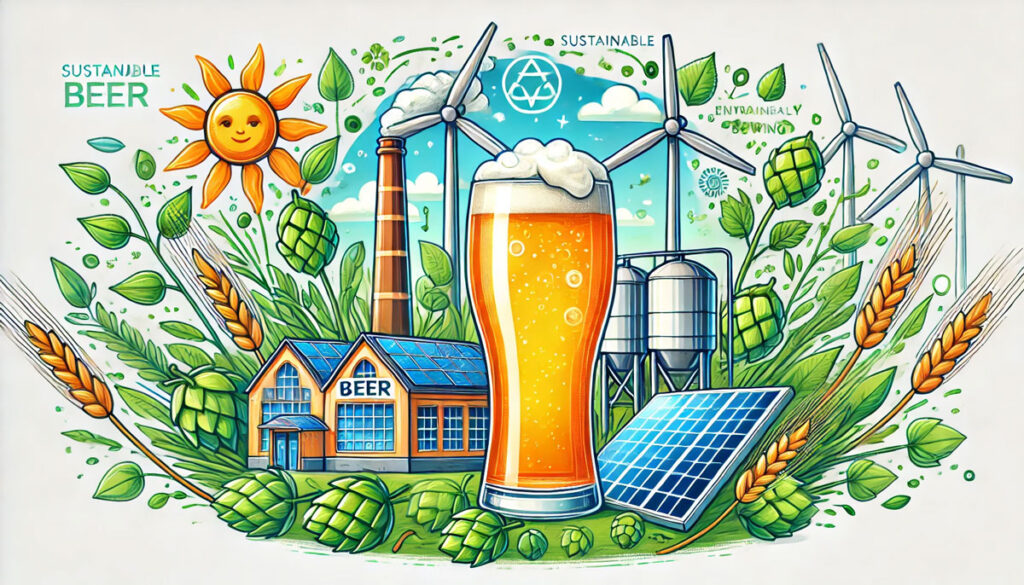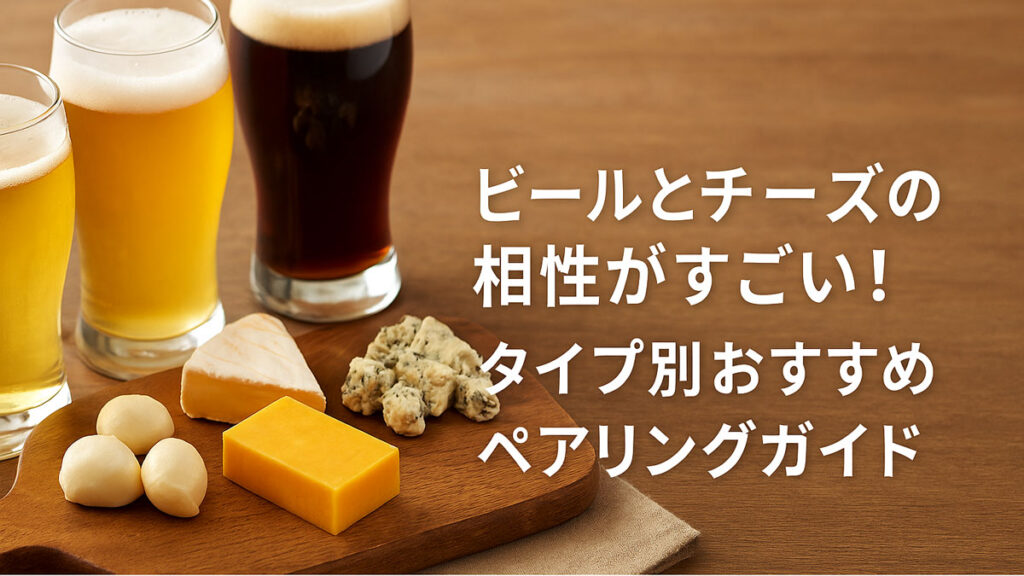「ビール検定って難しい?初心者でも合格できる?」そんな不安を抱えていませんか?
本記事では、ビール好きやクラフトビールに興味がある方に向けて、びあけんの概要や各級の違い、初心者でも実践しやすい勉強法、合格に役立つおすすめの教材までわかりやすく紹介します。
さらに、検定の知識を活かして日常のビール体験をより豊かにするヒントも満載!学びながら楽しめる“飲む資格”を、一歩ずつ楽しく攻略していきましょう。
ビール検定(びあけん)とは?|試験概要と人気の理由

ビール好きが資格を取る時代に
かつて「ビールの知識」は愛好家の間で語られるものでしたが、今では一般の消費者も楽しみながら知識を深められる資格制度が注目を集めています。その代表が「ビール検定」、通称「びあけん」です。
ビールを飲むだけでなく、ビアスタイルの違いや製法、歴史、文化的背景にまで関心を持つ人が増えている今、びあけんはそうした人々の「学びたい」「語りたい」ニーズに応える存在として人気です。
特にコロナ禍以降、自宅での飲酒スタイルやオンライン飲み会が定着したことで、「どうせ飲むなら、少し詳しくなってみたい」といった動機で受験する人が急増。趣味を深めながら取得できる手軽な検定として、クラフトビールファンを中心に広がりを見せています。
公式名称と「びあけん」の通称
正式名称は「日本ビール検定」。一般社団法人日本ビール文化研究会が主催する民間資格で、2012年にスタートしました。第1回の開催以降、年に1回(秋頃)に実施されており、累計受験者数は2万人を超える人気資格です。
「日本ビール検定」という名称よりも、受験者の間では親しみを込めて「びあけん」と呼ばれることが多く、SNSなどでも「#びあけん」での投稿が目立ちます。この略称が浸透したことも、受験のハードルを下げ、受けやすさにつながっています。
1級〜3級まであり、誰でも3級から受験可能であることから、初心者でも気軽に挑戦できるのが大きな魅力です。また、ビール検定の学習内容は、お店選びや注文時の会話の幅を広げる「実生活に活かせる知識」でもあるため、資格以上の価値を感じている人も多いのです。
受験者数・合格率の傾向(1級~3級)
以下の表は、日本ビール検定の受験者数と合格率の一例です(※2022年度発表の公式データを元に作成)。
| 級別 | 受験者数 | 合格率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 約2,300名 | 約85% | 初級者向け、趣味レベルでOK |
| 2級 | 約1,100名 | 約65% | 基礎知識の幅が問われる |
| 1級 | 約300名 | 約25% | マニア向け、記述式あり |
特に3級は正答率60%以上で合格できるため、初挑戦にぴったりです。逆に1級は記述式も含むため、かなりの対策が必要。とはいえ、1級合格者だけに与えられる「認定証」や「認定グッズ」も魅力で、熱意のある人たちにとっては目標となっています。
また、年に1度の開催であるため、計画的に学習を進める必要があります。勉強に使える公式テキストやアプリも充実してきており、次回開催に向けて今から準備を始めるのもおすすめです。
びあけん1級・2級・3級の違いとは?

試験範囲・難易度・出題傾向の比較
「びあけん」こと日本ビール検定は、3級・2級・1級の3段階で構成されており、それぞれ試験内容や難易度が大きく異なります。下記にそれぞれの特徴を比較した表をまとめました。
| 級 | 対象レベル | 出題形式 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 初心者〜一般向け | 四択マークシート | 基礎知識中心。趣味で楽しむ人にもおすすめ。 |
| 2級 | 中級者向け | 四択マークシート | 用語や製法、原料に関する詳細な知識が必要。 |
| 1級 | 上級者・ビールマニア向け | 四択+記述問題 | 出題範囲が広く、難易度も高い。合格者には認定証が発行。 |
3級は“趣味で学びたい人”にぴったりの内容で、ビール初心者でも取り組みやすいレベルです。一方、2級以上になると出題される知識がより実践的かつ専門的になり、ビールの歴史や製造工程、ビアスタイルの系統分類まで問われます。
1級に至っては、記述問題や応用的な知識が中心。たとえば「アメリカにおけるクラフトビールの潮流と日本の違い」など、単なる暗記では太刀打ちできない問題も登場します。
ビール初心者におすすめなのは何級?
「びあけんを受けてみたいけど、どこから始めればいい?」という方には、断然3級がおすすめです。難しすぎず、合格を目指しながらビールの基礎が自然と身につきます。
実際に3級の出題内容には、「ビールの主な原料は?」「ドイツ発祥のビアスタイルはどれ?」など、ビールを日常的に楽しんでいれば答えられる問題も多く含まれます。
「クラフトビールが好き」「飲み比べが趣味」といった方であれば、少し勉強するだけで2級にも手が届く可能性があります。ただし、1級は相当な準備が必要となるため、まずは3級から段階的にステップアップするのが現実的です。
合格ライン(正答率)と合格率の目安
びあけんは級ごとに合格基準と合格率が明確に設定されています。以下に参考となる目安をまとめました。
| 級 | 合格基準(正答率) | 合格率(目安) |
|---|---|---|
| 3級 | 60%以上 | 約85% |
| 2級 | 70%以上 | 約65% |
| 1級 | 非公開(記述含む総合評価) | 約20〜25% |
このように3級は高い合格率を誇りますが、1級は非常に狭き門となっています。そのため、無理せず自分のレベルに合った級を選ぶことが、モチベーション維持にもつながります。
また、1級を受験するには2級合格が前提条件となるため、初受験の方はまず3級・2級に挑戦することからスタートしましょう。
びあけんは年1回の開催(9月〜10月頃)なので、スケジュールを意識しながら計画的に準備を進めるのがポイントです。
初心者から始めるビール検定の勉強法

【ステップ①】まずは3級から挑戦しよう
ビール検定に興味を持ったら、最初の一歩として3級からの受験がおすすめです。3級は、日常生活の中で親しんでいるビールに関する基礎的な知識を問う内容となっており、過去の受験者からも「楽しみながら勉強できた」と高い評価を受けています。
具体的には、ビールの歴史・原料・醸造方法・ビアスタイルの特徴など、幅広い分野から出題されますが、選択肢形式のマークシート方式なので、暗記が苦手な人でもチャレンジしやすいのが魅力です。
また、3級は合格ラインが60%程度と比較的やさしく、「まずは受けてみよう」の気持ちでトライしやすい級です。「勉強」と身構えず、楽しみながら知識を広げていくことが合格の近道といえるでしょう。
【ステップ②】日常の“ビール習慣”を学びに活かす
びあけんの勉強は、机の上だけで完結するものではありません。普段のビールの飲み方そのものが、立派な学習時間になります。
例えば、飲む銘柄のラベルを見て「原産国」「スタイル」「アルコール度数」に注目したり、飲み比べをして「ラガーとエールの違い」を体感したりすることで、自然と知識が身についていくのです。
さらに、クラフトビール専門店や地ビールの取り扱いがある居酒屋では、スタッフに話を聞いてみるのもおすすめ。ラベルの裏やメニューの説明文からもヒントが得られます。生活にビールの「情報視点」を加えるだけで、学習効率が大きく変わるでしょう。
【ステップ③】過去問と公式ガイドブックで理解を深める
試験対策として定番なのが、公式ガイドブックと過去問の活用です。日本ビール検定の公式テキストは、「日本ビール文化研究会」監修のもと発行されており、3級〜2級の出題範囲を網羅しています。
テキストでは、基本的な知識に加え、世界のビール文化、日本のビール史、原料や醸造技術についてもわかりやすく解説されており、初心者でも読み進めやすい構成です。
また、過去問集や市販の問題集を活用することで、試験の出題傾向や難易度が掴めます。実際の選択肢のクセや、ひっかけ問題のパターンを知っておくと、当日の試験でも落ち着いて対応できます。
スマホを使った学習もおすすめです。びあけん対策アプリやクイズ形式のサイトを使えば、スキマ時間でも効率よく復習が可能。通勤中や待ち時間にこまめにチェックするだけでも、知識の定着度が上がります。
「インプット」と「実体験」を組み合わせた学習こそが、びあけん合格の近道です。
合格に役立つ!おすすめテキスト・サイト・アプリ

公式テキストブックと活用法
ビール検定(びあけん)対策として、まず手に入れたいのが公式のテキストブックです。これは日本ビール文化研究会が監修する唯一の公式教材で、3級・2級の出題範囲をカバーしています。毎年最新情報を反映した改訂版が販売されており、Amazonや書店で手軽に購入できます。
内容は、ビールの歴史・原材料・醸造工程・ビアスタイル・国内外の文化など、幅広く網羅されており、試験対策のみならず、読み物としても楽しめる構成です。
活用のポイントは、「一気に読む」よりも、「章ごとに小分けにして読む」こと。チェックボックスや赤シートなどを活用しながら、繰り返し復習することで知識の定着が格段に上がります。
また、巻末にある「練習問題」や「用語集」も、直前対策に非常に役立ちます。特に用語は頻出テーマが多く、覚えておくことで2級以降の対策にもつながります。
無料で学べるおすすめ学習サイト
「できれば費用をかけずに勉強したい」という方にとって、無料のオンライン教材は強い味方です。以下に、びあけん対策に使える代表的な無料学習サイトをご紹介します。
- びあけん.jp(公式)
過去の出題例や検定概要、受験者の声などが掲載されており、公式の雰囲気に慣れるには最適。 - クラフトビール東京|検定対策記事
試験の傾向や注目スタイルのまとめが詳しく、読んで楽しい解説も魅力。 - note・ブログ投稿(個人の受験体験記)
「びあけん 3級 体験談」などで検索すれば、リアルな勉強法や参考になる問題傾向を知ることができます。
これらのサイトを参考にしながら、公式テキストと照らし合わせて内容を整理すると、学習効果が高まります。中には図解や写真付きで解説されている記事もあり、視覚的に理解しやすい点もメリットです。
スキマ時間に学べるスマホアプリ(例:クイズ系)
忙しい人でも無理なく続けられるのが、スマホアプリを使った“スキマ学習”です。通勤中や待ち時間など、ちょっとした時間にクイズ感覚で知識を身につけられるのが魅力です。
おすすめは以下のようなアプリやツールです:
- Studyplus(スタディプラス)
学習記録の管理やモチベーション維持に。びあけん対策の独学記録として活用可能。 - Quizlet(クイズレット)
自分で単語帳を作れるほか、「beer検定」関連の公開セットも多数。反復学習に最適。 - びあけん対策アプリ(非公式)
Android向けやWebベースで公開されていることがあり、簡単な○×・選択問題で実力チェックができます。
特にQuizletなどは、自分の弱点だけを繰り返す学習がしやすいため、苦手克服にも効果的です。また、クイズ形式で繰り返すうちに、「このスタイルはドイツ系だっけ?」「原料に〇〇を使うのはどのビール?」といった問いに、自然と反応できるようになります。
“ながら勉強”や“反復練習”を積み重ねることで、自然と知識が定着しやすくなります。学習にまとまった時間が取れない方でも、アプリを使えば確実に一歩ずつ進めることができるでしょう。
ビール知識を実生活で活かす楽しみ方

外食・家飲みがもっと楽しくなる!銘柄の選び方
びあけんで学んだ知識は、日常の“飲む時間”をより豊かにしてくれます。たとえば外食時、メニューに並ぶ銘柄を見て「これはラガーだからキレが良いな」「こっちはIPAでホップが強いタイプだな」といったように、味の特徴を想像しながら選ぶ楽しみが広がります。
家飲みでも、季節や食事に合わせてビールを選ぶ楽しさが増します。寒い時期にはコクのあるスタウト、暑い日にはすっきりしたピルスナーなど、気分や料理に応じて最適な1本をチョイスできるのは、まさに“知識のある飲み手”の特権です。
特にクラフトビールの種類が多い昨今、ビールスタイルの理解があるだけでラベルの情報から味や香りを予測することができるようになります。「自分に合うビールって何だろう?」と考えるきっかけにもなり、飲むほどに世界が広がっていくでしょう。
醸造所見学やクラフトビールイベントへの応用
知識を深めたら、次は現場へ足を運んでみましょう。全国各地に点在するブルワリー(醸造所)では、見学ツアーや試飲イベントが開催されており、学んだ内容を“体験”として実感できる絶好の機会です。
特に、実際の原材料に触れたり、醸造設備を見たりすることで理解が格段に深まるだけでなく、ブルワー(醸造家)との会話を通じて「このスタイルはこういう意図で作った」という裏話を聞くことができるのも醍醐味です。
また、全国ではクラフトビールフェスや地ビール祭なども定期的に開催されており、複数の銘柄を一度に比較・体験できる貴重な場となっています。びあけんの知識があれば、「どの順番で飲むか」「このビールはどこの系統か」など、より深い楽しみ方ができるでしょう。
周囲に語りたくなる「うんちく力」も身につく
ビール検定の学習を通して得た知識は、日常会話でも活躍します。たとえば友人との飲み会で「実はこのスタイル、ドイツから始まった伝統があって…」とさりげなく話せば、ちょっとした“ビール博士”として一目置かれるかもしれません。
もちろん、ただの知識披露ではなく、会話のきっかけとして役立つ“うんちく”が豊富になるというのがポイント。銘柄の背景や製造過程を知っているだけで、自然と話題が広がり、お酒の席がより豊かで楽しいものになります。
さらに、SNSやブログなどで「飲んだビールの感想」や「びあけんの勉強記録」を発信することで、同じ興味を持つ仲間とのつながりも生まれるでしょう。知識を“自分だけの楽しみ”にとどめず、他者との共有を通じてさらに広げていけるのが、びあけんの大きな魅力です。
まとめ|びあけんは“学んで楽しい”資格

趣味と実益を兼ねたビール検定
「ビール検定(びあけん)」は、単なる資格試験ではありません。趣味を深めながら日常の楽しみを広げられる、実益のある“学びのツール”として、多くのビールファンから支持されています。
もともと趣味としてビールに親しんでいた方はもちろん、「何か新しいことにチャレンジしたい」「お酒の知識を身につけたい」と考える人にもぴったりです。日常の飲み方や会話がより豊かになるだけでなく、イベントや旅行の楽しみ方にも深みが加わります。
また、びあけんは公式な認定資格であり、合格証が発行されることで「自分の学びの成果」が形として残るのも大きな魅力です。趣味と実益が両立する資格は、そう多くありません。
「合格」は通過点!奥深いビールの世界へ
びあけんは3級から始まり、2級、1級とステップアップしていく形式ですが、「合格すること」が最終目的ではなく、そこから始まる“ビールの世界を深く知る旅”が本質ともいえるでしょう。
受験勉強を通してビールの原料や歴史、製法を知ることで、普段何気なく飲んでいた一杯のビールが、まったく違った視点で味わえるようになります。
「この苦味はホップ由来だな」「このスタイルはベルギー系かも」など、感覚と思考が結びついていくことで、まるで「テイスティングができるようになった」ような自信も身につきます。
さらに、学んだ知識を誰かに伝える楽しさや、新たなクラフトビールとの出会いが、日常のちょっとした“ご褒美”に変わっていくのです。
まずは一歩、3級から始めてみよう
「気になるけど難しそう」「勉強って苦手…」と思っている方も、心配は不要です。びあけん3級は初心者にもやさしく、誰でも気軽に挑戦できる内容です。
過去問題や公式テキストを見れば、「これなら覚えられそう」と思える内容が多く、日々の生活とつなげて学べることが最大の特徴です。
試験勉強と構えず、いつもの家飲みを「知識を使ってみる実践の場」にすれば、自然と学びは定着していきます。そして3級に合格したとき、ただ“資格を取った”以上の喜びがきっと味わえるはずです。
びあけんは楽しく飲みながら、楽しく学べる資格です。ぜひ、次の一杯から“学びの視点”をプラスして、新しいビールの世界へ一歩踏み出してみてください。